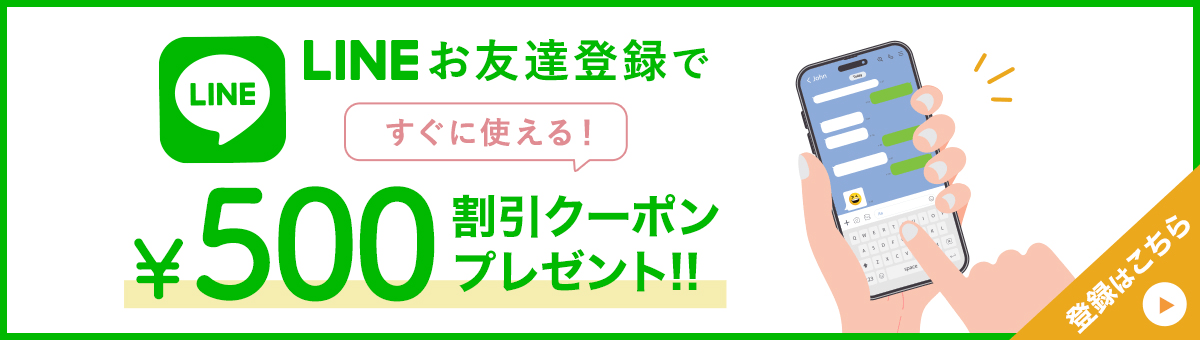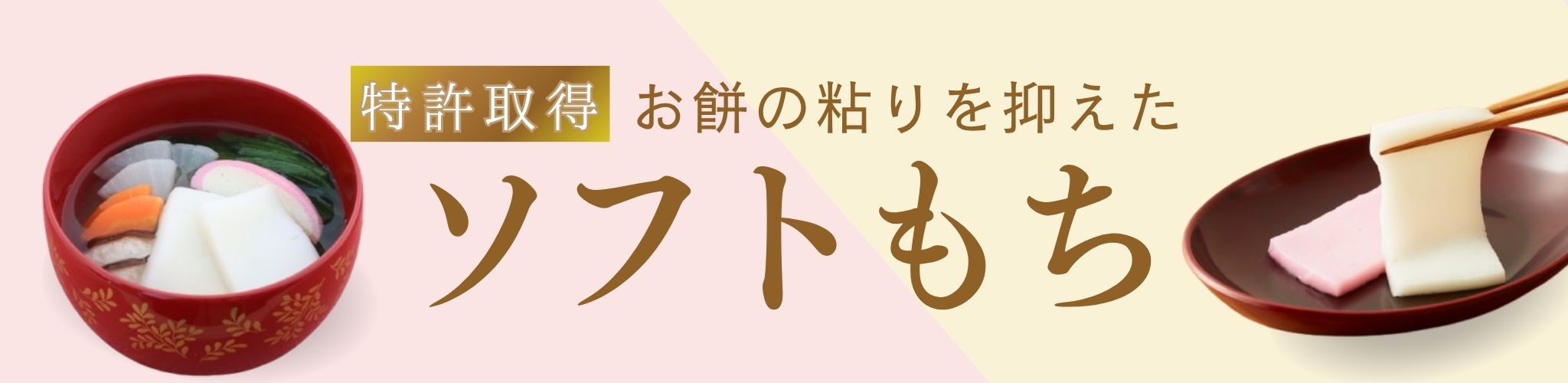高齢者にとって、誤嚥は非常に危険な問題です。
誤嚥が発生すると、食物や液体が気管に入ってしまい、肺炎などの重篤な症状を引き起こす可能性があります。
特に、嚥下機能が低下している高齢者は注意が必要です。
まず、誤嚥を防止するためには、食事の際の姿勢に気を付けることが重要です。背筋を伸ばし、安定した姿勢で食べることで、嚥下を助けることができます。
また、食事の内容も工夫が大切です。柔らかい食材や飲み込みやすい食材であることはもちろんですが、食べ物の認識ができて美味しそうと思ってもらえる食事は食べる準備ができるので、誤嚥の予防につながります。
さらに、介護従事者や家族介護者は、高齢者が食べる際にそばにいて、様子を観察しましょう。普段とは違う様子があれば、すぐに対応できる体制を整えることが必要です。
日常的な注意を払い、誤嚥を防止する方法を取り入れることで、高齢者の健康を守ることができるでしょう。
今回は高齢者の誤嚥防止と予防策について解説します。
お試し12食セット
価格:5,800円(税込)
UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる
人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらかちらし寿司」の2食プレゼント付きの12食セットです。

誤嚥とは何か?
誤嚥とは、食べ物や飲み物が誤って気道に入ってしまう現象です。
通常、食べ物は食道を通って胃に運ばれますが、嚥下の際に誤って気管に入ると、呼吸を妨げてしまいます。特に高齢者では、嚥下機能が弱くなるため、誤嚥のリスクが高まります。誤嚥が起こると、咳込んだり、息苦しさを感じることがあります。
また、これが原因で誤嚥性肺炎が発症することもあり、場合によっては命に関わる事態になります。
高齢者は免疫力が低下しているため、感染症にかかりやすく、誤嚥からの影響に注意が必要です。
高齢者が誤嚥しやすい原因

高齢者が誤嚥しやすい原因は幾つかあります。
まず、加齢による嚥下機能の低下が挙げられます。年齢を重ねるごとに、食道の筋肉が弱まり、食物を飲み込む力が弱くなります。このため、食事中に食物が喉に詰まりやすくなります。
次に、神経系の疾患も大きな要因となります。パーキンソン病や脳卒中の後遺症など、神経に関連する病気によって、嚥下反射が麻痺する場合があります。この結果、誤嚥が生じるリスクが高まります。
また、口腔ケアの不足も問題です。口腔内の衛生状態が悪いと、食事が喉に詰まりやすくなるだけでなく、誤嚥性肺炎のリスクも増加します。これらの要因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
お試し12食セット
価格:5,800円(税込)
UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる
人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらかちらし寿司」の2食プレゼント付きの12食セットです。

誤嚥防止のための基本対策
誤嚥防止のための基本対策は多岐にわたりますが、まずは食事の際の適切な姿勢が重要です。
高齢者は、背筋を伸ばして座ることが推奨されます。座って食べることで、食べ物がスムーズに食道に入るため、誤嚥のリスクを大幅に減少させることができます。
さらに、食事の内容にも気を配る必要があります。個々の高齢者の嚥下状態に適した無理のない食材を食べやすく調理することが、誤嚥防止に繋がります。
食事の際は、声をかけ目を覚まして意識がはっきりしているか確認し、加えて食事中は会話を控え、意識を集中させることも大切です。嚥下に専念することで、より安全に食事を摂ることが可能になります。
これらの基本対策を取り入れることにより、高齢者の誤嚥を防止し、健康を守ることができます。
適切な食事の姿勢
適切な食事の姿勢は、高齢者が安全に食事を摂るために欠かせない要素です。正しい姿勢をとることで、嚥下機能が向上し、誤嚥のリスクを減らすことができます。
一般的には、椅子や車椅子の場合、深く腰掛けて座り、背筋を伸ばして首が少し前に傾いた顎をひいた状態にすることが基本です。足は床にしっかりとつけ、安定した姿勢を保ちましょう。
麻痺がある場合は、上体が倒れないように麻痺側の手をテーブルの上に乗せます。麻痺があり食事介助をする場合、食べ物は麻痺のない側の口から入れるようにし、誤嚥やむせが起こらないように、声かけしながら食べ物を口に運びます。
嚥下体操やリハビリ
嚥下体操やリハビリは、高齢者の誤嚥を防ぐために非常に重要な役割を果たします。
特に、嚥下機能が低下している方にとっては、日常的にこれらの運動を取り入れることが健康維持につながります。 リハビリ専門家による指導も有効です。介護施設や病院では、専門的なリハビリを受けることで、より効果的に嚥下機能を向上させることができます。
自宅でできる簡単な運動もあるため、励ましながら家族と一緒に取り組むと良いでしょう。
健康な食生活と併せて、嚥下体操やリハビリを実践することで、高齢者の誤嚥を減少させ、より安全な生活を送るための一助になります。
食事の工夫
食事の工夫は、高齢者の誤嚥防止において非常に重要な要素です。
まず、食材の選択が大切です。柔らかく、噛みやすい食材を中心にメニューを考えましょう。
水分の少ないパンやカステラ、口の中にひっつきやすい海苔やワカメ、弾力のある蒲鉾やこんにゃくなどは一般的に高齢者が飲み込みにくい食材ですので小さく切るなどして食べやすくしたり、場合によっては避けるようにしましょう。
調理方法では、煮物やスープは、柔らかくなりやすく、飲み込みやすいのでおすすめです。摂食嚥下は「おいしそう」「食べたい」という信号が脳に送られると食欲が湧いて摂食行動が促されます。
見た目に食べ物の形があって彩りよく食欲をそそられるような工夫をしましょう。
飲み物についても、嚥下反射が遅いために誤嚥しやすい方はとろみをつけることで、飲み物がゆっくりと喉に送られ飲み込むタイミングが取りやすくなります。
とろみの強さは対象者に合わせる必要がありますが、強すぎると窒息の原因にもなるので注意が必要です。
また、固形物と水分を交互に飲み込むと嚥下反射を誘発し咽頭の食物残渣を減らすことができます。
まずは食事前に水分を取って口腔内と食道を湿らせて食事中は固形物をひと口毎あるいは数口毎に水分をとり、食事の最後にも水分をとるよう状況に応じて行うとよいでしょう。
これらの工夫を通じて、食事の安全性を高め、高齢者の健康を支えていきましょう。
具体的な誤嚥防止トレーニング

高齢者の誤嚥を防ぐためには、日常的なトレーニングが効果的です。
具体的には、嚥下機能を強化するためのエクササイズを取り入れることが勧められます。
トレーニングは、介護者が一緒に行うことで、安心感を与え、継続的に実施しやすくなります。日常生活に取り入れ、効果を実感していきましょう。
嚥下体操の実践方法
嚥下体操は、高齢者の嚥下機能を向上させるための有効な手段です。
まず、簡単なストレッチから始めましょう。首を前後左右にゆっくりと動かします。その後、肩を上げ下げして動かします。これにより、首周りの筋肉がほぐれ、嚥下に必要な筋肉がリラックスします。
次に、舌の運動です。口を大きく開けて舌を出し、上に持ち上げたり、下に下げたりします。その後、舌を左右に動かします。
また口の中から左右のほうに空気をためて押すと口に隙間ができて口が開きやすくなります。この動作を繰り返すことで、舌の筋力を強化できます。
最後に、唇の運動です。唇をしっかり閉じてから、「あー」や「いー」などの母音をできるだけ長く声出しします。これにより、口周りの筋肉が鍛えられ、嚥下がスムーズになります。
これらの体操を毎日続けることで、嚥下機能の向上に繋がります。無理のない範囲で行い、楽しんで取り組むことが大切です。介護者がともに行うことで、より効果的なトレーニングとなります。
口腔ケアの重要性と方法
高齢者にとって、口腔ケアは誤嚥防止において非常に重要な役割を果たします。
口腔内の衛生状態が悪化すると、食べ物の残りカスや口腔内の細菌によって、誤嚥のリスクが高まります。そのため、定期的な口腔ケアが必要です。
まず、口腔内を清潔に保つためには、毎日のブラッシングが基本です。適切な歯や舌の磨き方を学び、虫歯や歯周病を予防することが大切です。
また、義歯を使用している方は、義歯の洗浄も忘れずに行いましょう。
さらに、口腔内が乾燥すると嚥下が困難になるため、水分補給も意識的に行うことが重要です。口腔内を湿らせるために、うがいや噛むことで唾液を出すことを意識して行うと良いでしょう。
また、定期的に歯科医を受診することで、専門家のアドバイスを受け、適切なケアを行うことができます。このように、口腔ケアをしっかり行うことで、誤嚥のリスクを減少させ、高齢者の健康を守ることができるのです。
お試し12食セット
価格:5,800円(税込)
UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる
人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらかちらし寿司」の2食プレゼント付きの12食セットです。

今後の注意点

今後の注意点として、まず食事の環境を整えることが挙げられます。静かな場所でリラックスできる雰囲気を作ることで、高齢者が安心して食事を楽しむことができます。
また、周囲の音や人の動きが気にならないよう配慮することが重要です。
次に、食事の速度に気を付ける必要があります。急いで食べると、誤嚥のリスクが高まります。高齢者に対しては、ゆっくりと時間をかけて食べるように促すことが求められます。
介護者は、食事を一緒に楽しむことで、コミュニケーションも深めることができるでしょう。
さらに、嚥下トレーニングを取り入れることも有効です。専門家の指導のもとで行うことで、嚥下機能の改善が期待できます。高齢者の状態に応じた適切な食事や訓練を行い、今後の誤嚥予防に積極的に取り組むことが大切です。
誤嚥が起きた場合の対応
誤嚥が起きた場合は、迅速に対応することが重要です。
まず、高齢者が咳き込んでいる場合は、自然に異物を吐き出させるようにしましょう。咳は体が異物を排除しようとしているサインですので、無理に妨げないようにします。
もし咳が止まらなかったり、苦しそうな表情をしている時は、背中を軽く叩いてあげると良いでしょう。この際、大声で驚かせないように、優しく接することが必要です。
高齢者が誤嚥して自力で吐き出せない場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
応急処置として、背部叩打法(タッピング法)または腹部突き上げ法(ハイムリック法)を実施します。腹部突き上げ法(ハイムリック法)は意識のない人には実施できないので、背部叩打法(タッピング法)を実施します。
また、高齢になると異物を外へ吐き出そうとする反応が弱くなり咳き込んだりむせるというサインがなくても「サイレント・アスピレーション」(静かな誤嚥)という状態で誤嚥している場合があります。
呼吸が早くなったり、表情がけわしくなったり、声のかすれ、喉の違和感、原因不明の熱などの症状により誤嚥が発見されることがありますので、普段からこまめに観察することが大切です。
誤嚥が起きた時は、冷静に対応し、その後は医療機関での受診を考慮しましょう。特に、高齢者の場合は、誤嚥が原因で他の健康問題が発生することもありますので、慎重に対処することが求められます。
継続的なケアの重要性
継続的なケアの重要性は、高齢者の健康を守る上で欠かせません。特に、誤嚥防止においては、日々の観察とケアが必要です。
定期的に食事内容や嚥下機能を見直すことで、小さな変化に気づきやすくなります。
また、介護従事者や家族介護者は、高齢者とのコミュニケーションを通じて、気持ちや困りごとを理解することが大切です。
安心感が持てる環境を作ることで、食事を楽しむ意欲を引き出せます。 さらに、嚥下トレーニングや食事の際の姿勢の確認も、継続的なケアに含まれます。
これらを日常的な習慣として実施することで、誤嚥のリスクを低減し、健康を維持することができるでしょう。
まとめ
高齢者の安全な生活を守るためには、誤嚥防止策をしっかりと実施することが大切です。誤嚥は、特に嚥下機能が低下している方にとって、命に関わる重大なリスクとなります。
適切な食事の姿勢や、食材の工夫をすることで、誤嚥を防ぐことができます。
介護従事者や家族介護者が高齢者の食事に注意を払うことで、未然に危険を防ぐことが可能です。また、高齢者自身にも、嚥下体操や適切な飲み込みのテクニックを学んでもらうと良いでしょう。
このように、日々の生活の中で誤嚥を防止する意識を持つことで、高齢者の健康を保ち、安心して生活していただくことができます。
これからも誤嚥防止の重要性を忘れずに、多くの方がこの問題に取り組むことを願っています。
お試し12食セット
価格:5,800円(税込)
UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる
人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらかちらし寿司」の2食プレゼント付きの12食セットです。

監修者
上田 稚子(Ueda Wakako) 管理栄養士
大学卒業後、管理栄養士として亜急性期病院にて幅広いライフステージ、様々な疾患に応じた栄養指導をしてきました。
現在は、名阪食品株式会社にて介護食ブランド「そふまる」の研究開発に携わっています。