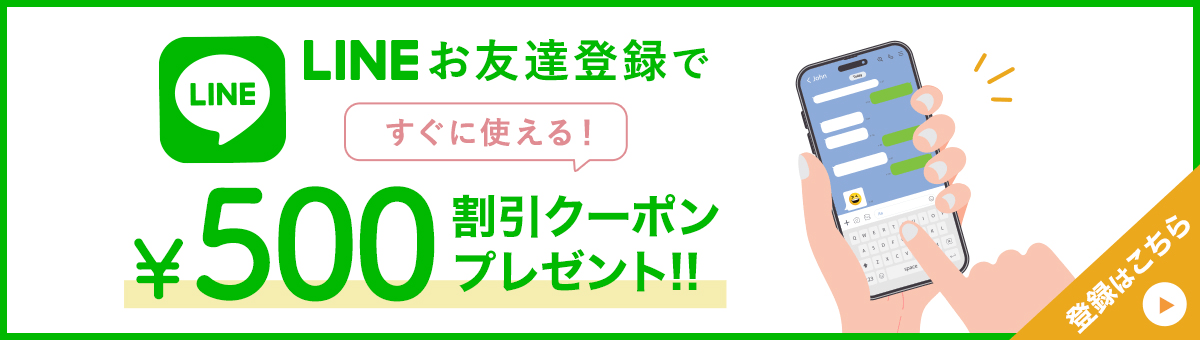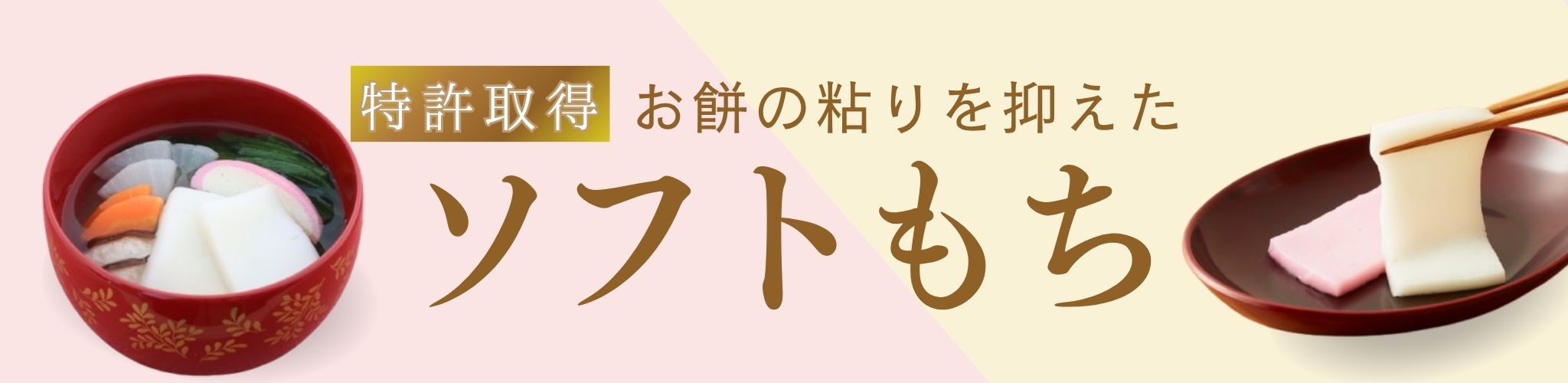こんにちは!介護食そふまるライターチームです。
「塩分を控えましょう」とよく言われますが、実は“ナトリウム不足”にも気をつける必要があります。特に高齢の方は、体内の水分や電解質のバランスが崩れやすく、知らないうちに低ナトリウム血症を引き起こしてしまうことがあります。低ナトリウム血症を防ぐためには、日々の食事の中で、無理なくナトリウムを取り入れる工夫が大切です。塩分の摂りすぎに配慮しながら、体に必要な栄養をしっかりと補っていきましょう。
今回は、高齢者の方に役立つ、低ナトリウム血症を予防するための食事のポイントをご紹介します。ご本人はもちろん、ご家族や介護をされている方も、ぜひ参考にしてみてください。

お試し12食セット
価格:5,800円(税込)
UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる
人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらかちらし寿司」の2食プレゼント付きの12食セットです。

低ナトリウム血症とは
私たちの体には、体の中の水分バランスを整えたり、筋肉や神経の働きをスムーズにしたりするために、「ナトリウム」という成分が欠かせません。このナトリウムが少なくなりすぎた状態を「低ナトリウム血症」といいます。
特に高齢の方は、年齢とともに体の調節機能が衰えやすくなり、ナトリウムのバランスも崩れやすくなります。日々の体調の中で「なんとなくだるい」「頭が重い」と感じることが、実は低ナトリウム血症のサインだった…ということもあります。
まずは、低ナトリウム血症がどんな状態なのかを知っておくことが、安心につながります。
低ナトリウム血症の定義と診断基準
血液中のナトリウム濃度が135 mEq/L未満の場合を低ナトリウム血症といい、血液検査で診断されます。症状や飲水量、服薬状況などとあわせて原因を探ります。調子が悪いと感じたら、医療機関へ相談しましょう。
低ナトリウム血症の症状
初期は疲れやすさ、頭の重さ、食欲不振などあいまいな症状が多いですが、進行すると精神的な混乱や言語障害、さらにはけいれんや意識障害など重篤な状態になることもあります。高齢者の方は、こうした変化をご自身でうまく伝えられない場合もあります。ご家族や介護されている方が「いつもと様子が違う」と感じたら、早めに対応することがとても大切です。
低ナトリウム血症の主な原因
高齢の方が低ナトリウム血症になりやすいのには、いくつかの理由があります。主な原因は、以下のようなものが考えられます。
年齢とともに腎機能が衰え、ナトリウムや水分の調整がうまくいかなくなることがあります。
利尿剤・降圧剤などのお薬の影響
水分を排出するタイプのお薬は、ナトリウムも一緒に出てしまうことがあり、注意が必要です。
水分の摂りすぎ
「たくさん水を飲んだ方が良い」と思って、必要以上に水分を摂ることで、体内のナトリウムが薄まってしまうことがあります。
長引く下痢や嘔吐
体の外に水分と一緒にナトリウムも失われてしまうため、体内のバランスが崩れやすくなります。
ホルモンバランスの異常
一部のホルモン異常が、体の水分・ナトリウム調整に影響する場合もあります。
原因は複数重なることも多く、気になる症状があれば医療機関に相談してください。
高齢者が特に注意すべき点
高齢者は体の水分調整機能や腎機能が弱まりやすく、また薬の影響も受けやすいことから、低ナトリウム血症になりやすい傾向があります。
低ナトリウム血症が高齢者に与える影響
ナトリウムは、体の中で水分の調整や神経の働きに関わる、大切な成分です。その量が多すぎたり少なすぎたりすると、体にさまざまな不調が出てしまうことがあります。
水分のバランスが崩れることで、体がだるくなったり、手足がむくんだりすることがあります。
精神的な混乱や意識障害
特に高齢者は、軽い混乱や判断力の低下が見られることがあり、認知症と間違えられることもあります。
筋力の低下・ふらつき
筋肉にも影響が出るため、転倒やけがのリスクが高まります。
どれも日常生活に影響を与えるため、早めの気づきと対処がとても大切です。
気をつけたいこと
高齢の方が健康を保つために、次のような点に注意しましょう。
のどが渇いていなくても水分補給は大切ですが、必要以上の摂取はかえってナトリウム不足を招くことがあります。
食事はバランス良く、ナトリウムを適度に取り入れる
減塩も大切ですが、ナトリウムが不足しすぎないよう注意しましょう。みそ汁や漬物などを上手に活用するのも一つの方法です。
定期的な健康チェックを受ける
血液検査などでナトリウム値を確認し、医師からのアドバイスを受けながら体調管理をしていきましょう。
高齢者の体はちょっとした変化にも敏感です。だからこそ、日々の食事や水分の摂り方にほんの少し目を向けるだけで、体の調子が整いやすくなります。ご自身だけでなく、ご家族や介護に関わる方とも一緒に取り組めると安心ですね。
低ナトリウム血症に対応する食事の基本

低ナトリウム血症予防の食事では、ナトリウムを適度に摂りつつ、栄養バランスを整えることが欠かせません。新鮮な食材を中心に、加工食品の塩分には特に注意しましょう。家族や介護者の支えも活用して、続けやすい健康的な食生活を目指しましょう。
低ナトリウム血症対策のための食材選び
低ナトリウム血症を防ぐためには、どんな食材を選ぶかが重要です。新鮮な野菜や果物はナトリウムが少なく、ビタミンやミネラルを豊富に含むため、毎日の食事にしっかり取り入れたいものです。ほうれん草やブロッコリーは栄養価が高く、特におすすめです。
また、玄米や全粒粉パン、豆腐などの穀物や豆製品も体にやさしく、ナトリウムを控えめにできる良い選択肢です。魚や肉は、蒸す・焼くなどシンプルな調理法で塩分を控え、ハーブやスパイスで風味付けを工夫すると、健康的に楽しめます。
具体的な食事メニュー例
食事だけでなく、室内環境の管理も熱中症予防には欠かせません。
・全粒粉トースト
・アボカドとトマトのサラダ
・無糖ヨーグルト
・季節のフルーツ
◆昼食
・野菜たっぷりローズマリー蒸し鶏
・緑黄色野菜の副菜(ほうれん草、ブロッコリーなどの和え物や炒め物)
・カレースープ(じゃがいも・玉ねぎ・トマト・ズッキーニ・ツナ缶等)
◆夕食
脂ののった焼き魚(鮭、鯖)
レモンやお酢を使った大根なます
かぼちゃのそぼろ煮又は、ひじきと大豆の炒め煮
豆腐とワカメの味噌汁
ナトリウムを適度に摂りながら、栄養をしっかり補う工夫をしましょう。
食事の際の具体的な注意点
調理では、塩分を控えめにしつつ、ハーブやスパイスを上手に使うと味に変化が出て満足感が増します。缶詰や冷凍食品など加工品を使う際は、成分表示でナトリウム量を確認し、なるべく減塩タイプを選びましょう。
外食時は調味料を別にしてもらったり、スープやソースの量を控えめにしたりする工夫も効果的です。日々の小さな工夫が、低ナトリウム血症の予防と管理につながります。家族や介護者と協力しながら、無理なく続けていきましょう。
日常生活での注意事項
低ナトリウム血症の管理には、毎日の生活習慣を見直すことも大切です。食事の塩分量や水分摂取を適切に調整し、定期的な健康チェックを受けることで、安心して過ごせます。家族や介護者と協力しながら、無理のない範囲で続けていきましょう。
ナトリウム摂取量の管理方法
新鮮な食材を選び、加工品やスナックを控え、調味料は塩分を減らしてハーブやスパイスで味付け。塩は計量して使い、少しずつ減らすと味覚が慣れて自然に調整できます。
水分補給とその重要性
高齢者は喉の渇きを感じにくく、水分不足になりやすいため、意識的な水分補給が必要です。特に暑い日や運動後はこまめに水分をとるようにしましょう。水だけでなく、スープや果物、野菜からも水分を補うことができます。一度に大量に飲むのではなく、少しずつ何回かに分けて摂取するのが理想的です。適切な水分補給は体のナトリウムバランスを整える助けになります。
適切な体重管理の方法
毎日同じ時間に体重測定をし、変動を把握しましょう。バランスの良い食事を心がけ、軽い運動を取り入れると代謝が促進され、健康維持につながります。家族や介護者と一緒に取り組むと続けやすいです。
購入はこちら 購入はこちら
購入はこちら
まとめ
今回は、高齢者の方にとって注意が必要な「低ナトリウム血症」と、その予防につながる食事についてご紹介しました。
ナトリウムは体の水分バランスや神経・筋肉の働きに関わる大切な成分です。特に高齢になると、必要な栄養素が不足しやすくなるため、毎日の食事の中でナトリウムを適度に摂ることが大切です。塩分を控える必要がある方もいらっしゃる中で、無理なく取り入れる工夫や、家族・介護者のサポートも健康維持に役立ちます。
安心して毎日の食事を楽しみながら、低ナトリウム血症のリスクを防ぎ、健やかな生活を続けていきましょう。
監修者
上田 稚子(Ueda Wakako) 管理栄養士
大学卒業後、管理栄養士として亜急性期病院にて幅広いライフステージ、様々な疾患に応じた栄養指導をしてきました。
現在は、名阪食品株式会社にて介護食ブランド「そふまる」の研究開発に携わっています。